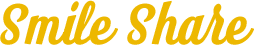働き方・人材採用アドバイザー
働き方カイカクは、企業にも、働くヒトにも、周りの環境にもプラスの効果を生み出します!
ワークライフバランス実践と啓発を目的に起業。女性や高齢者・障がい者の働き方をサポート実績多数。行政との連携多数で働き方検討会(経産省+厚労省)にも招致実績あり。ワークライフバランス、働き方に関する啓発セミナーや講演は年間30本を越える。現在人材コンサルタントとして、働き方アドバイス等、企業内の組織に入り人材育成のしくみを構築し、人材面からの仕事の効率化等をマネジメントしている。ロジック系のスキルアップも得意。